2018年8月17日のニュージャージー州での無罪判決に引き続いて、アメリカ オハイオ州の控訴審裁判所が、2018年10月5日、一審の陪審有罪判決を破棄し、再審理を命じました(IN THE COURT OF APPEALS OF OHIO SIXTH APPELLATE DISTRICT SANDUSKY COUNTY/State of Ohio v. Chantal N. Thoss /Court of Appeals No. S-16-043 Trial Court No. 15 CR 57)。
オハイオの事件は、生後6カ月の赤ちゃんのベビーシッターが、オムツを替えようとしてソファに赤ちゃんを置いて、少しその場を離れたところ、赤ちゃんがソファから落下した後、急変したというものでした。日本でも同じような低位落下が問題となっている裁判が、何件も係属しています。
一審の検察側証人だった小児科医は、事件当日に「赤ちゃんの症状は揺さぶりによるもので、被告人がその犯人だ」と決めつけていました。典型的なSBS仮説による意見です。その小児科医の意見を鵜呑みにした捜査機関は、揺さぶりを否定するベビーシッターの供述を無視し、その小児科医の意見のみを根拠に、ベビーシッターを起訴したのです。
実は、その赤ちゃんの初期治療に当たった救命医たちは、虐待の証拠はないと判断していました。検察側小児科医のみが、虐待だと決めつけていたのです。しかも検察側小児科医は、赤ちゃんに古い慢性血腫があることを無視していました。頭蓋内に古い血腫があった場合には、軽微な衝撃で再出血を生じてしまうリスクが高くなることはよく知られています。
一審の陪審は、この小児科医の証言を信じて有罪とされ、ベビーシッターは禁錮8年を言い渡されてしまいました。しかし、控訴審は、小児科医が赤ちゃんの古い血腫を無視しているのは不合理であること、ベビーシッターに動機はなく、その供述が信用できること、他にベビーシッターによる虐待の痕跡が全くないことなどを重視し、陪審の証拠判断は明白な誤りであるとしたのです。日本の裁判でも参考になる判断です。
なお、判決は、弁護側の専門家証人が、「赤ちゃんの症状だけから虐待を受けたと判断されたことは驚きである」とし、「医師の役割は、傷害を解釈し、情報を捜査官に与えて補助することであっても、捜査官となって犯人が誰かを特定することではない」と証言した部分を詳細に引用しています。その引用の背景には、検察側小児科医の証言が、医師としての領域を明らかに超越してしまっているという判断があったものと思われます。
ちなみに、この小児科医は、別の事件で、保育施設で3歳児の転倒による大腿骨折を虐待だと決めつけた意見書を提出しました。この小児科医は、州のために虐待事案の調査に協力し、意見書を提供する契約をしていたのです。その意見書のために、保育担当者は、解雇され、起訴されてしまいました。しかし、その事件は弁護側専門家証人が、小児科医の意見書には多くの誤りがあると指摘したことから、検察が起訴を取下げたのです。現在、保育担当者は、その小児科医師を相手に損害賠償の裁判を提起しています。
捜査機関に協力する医師の役割やその意見の在り方については、様々な問題がありますが、日本でも今後真剣な検討が必要であることは間違いありません。

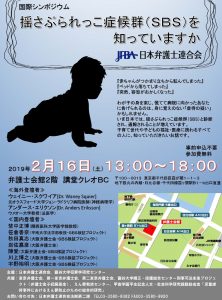
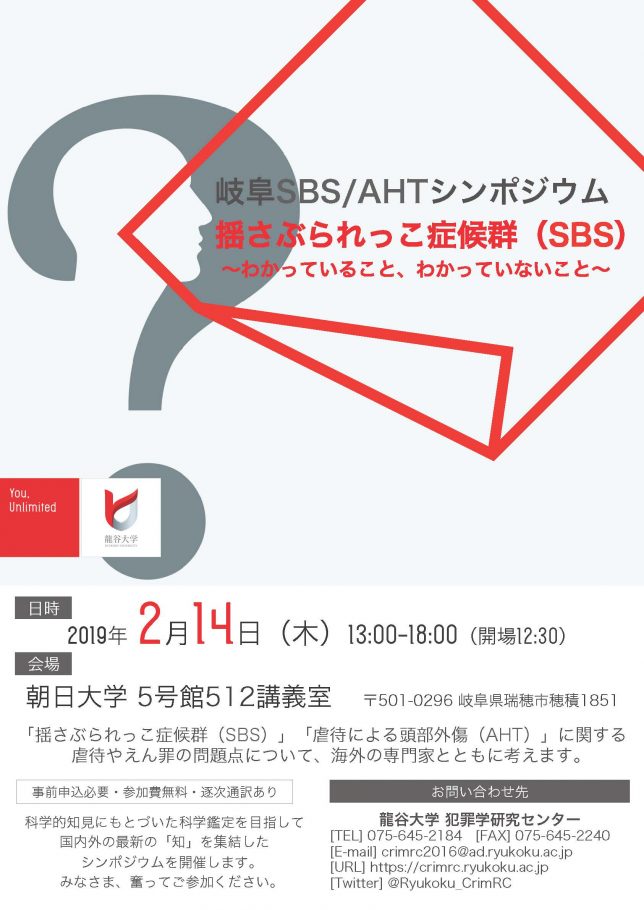
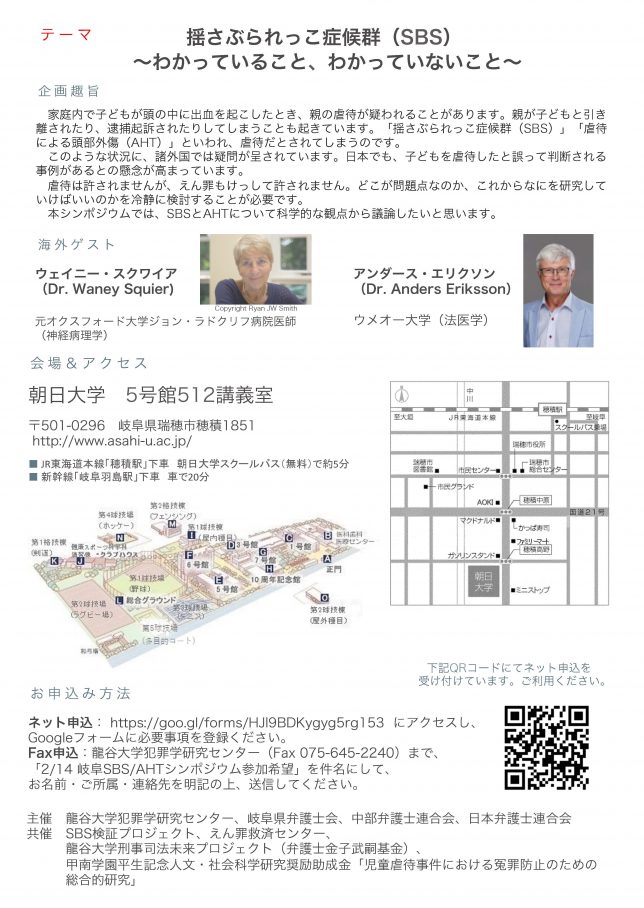
秋田_ページ_1-1-644x911.jpg)